4-5 吾加(五箇)の手の内
前回手の内の五癖について書きましたが、今日は竹林派の奥義から吾加(五箇)の手の内について、我流の解説をします。押手の手の内には5つの秘伝があり、単に5つ有るという意味と、我が力を加える合えるべきべきものとして「鵜の首」「鸞、卵(らん)中」「三毒」「骨法陸」「呼立り(ああたったり)」の5つがあります。
1)鵜の首
「鵜の首」の手の内と云うのは、押手をカラスに喩えるのと同様に、大三などで弓を押す形が、弓に直角であり剛弱所(手首の脈所)で曲がって水平になる形が鳥の首に似ていることから来ています。また、鵜匠が飲み込んだ魚を吐かせるときのように、親指と人差し指の股は開き、親指と小指を閉めることを、「上開下閉」と云います。
2)らん中
らんは鳥の雛のこと、あるいは卵のことです。押手はむやみに堅く握り締めるばかりでは、かえって鋭い押しにならず、鳥の雛を持つように、あるいは卵を握るように、丸く柔らかくして調子良く握り込むのが鋭い押しになることを教えたものです。ゴルフでも同じように、卵を握るように、あるいは小鳥を握るように柔らかく握りなさいと云われてます。
3)三毒
押手の3本の指は、小指を貧欲に締め、親指を「しんい」(語句不明)と云う憤怒の気持ちで締め、愚痴愚痴と薬指を締めるのが三毒強しの教えと云われていますが、難解でありよく判りません。これはひたすら強く握る教えであり、上記のらん中の柔らかく締めるのと矛盾しているように思われます。ただむやみやたらに強く握るのとは違ようです。
4)骨法陸
「骨法陸」の手の内は、骨格に合わせて直角に(陸)作用させることを云い、五重十文字の一つともいえます。押手の天文筋を合わせ、親指の掌根を直角にして中押しとするのはこの形のことでしょう。
5)呼立(ああたったり)
「呼呼立り、ああ立ったり」の手の内と云うのは、赤ちゃんが掴まって立ち上がるときの無邪気な握り方の手の内であり、全ての極意を達成した達人が最後に到達する無為無策で最高の手の内のことを云います。赤ちゃんが掴まって立ち上がったとき、親がああ立ったりと云って喜ぶことからこう云われていますが、赤ちゃんに弓が引けるわけじゃなし、還暦と同じように名人だけが最後に到達する、最も単純な規範に戻ろうとする極意でしょう。
古書では、この5つの手の内を説明するだけで、どれが最も良いとは書いていません。、これを「時の手の内」といい、自分に合うものを理解して行えといっているように思います。
櫻井 孝 | 2001/09/03 月 00:00 | comments (3)
| -

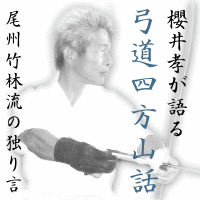



コメント
そう、そうなのです。僕もこれが疑問でした。わざわざ、初勘の巻に鵜の首と鸞中、父母の巻に三毒と骨法陸と呼立たり と分けて解説している。これが疑問でした。どうしてわざわざわけるのか。
初勘の巻が、どうも初学者の基本の部分の解説で、射を構成する大原則の基本を書いてあり、父母の巻に至っては、なかなか難解な部分が多く出てきますので、僕のその時の解釈では、初心者の内から三毒と骨法陸と呼立たりを教えると、難しすぎて混乱するから、基本軸がしっかり出来上がってから、それらを教えていく、という風に分けたのかな、と思っていました。
しかし、手の内の中にも、
土体黄色中四角
水体黒色北円形
木体青色東団形
火体赤色南三角
金体白色西半月
の五輪砕が出てきて、これは父母の巻まで読み進めないとわからないですね。びっくりしながら引き込まれるように読ませていただいております。
お察しの通り、僕は尾州竹林流とはちがいます。何流、というわけでない、弓道教本にのっとった正面打ち起こしの引き方です。ただ、射法訓の理解をしようとして行き当ったのが、やはり、『尾州竹林流 四巻の書講義録』と、松井巌先生の書かれた論文です。
まさに尾州竹林流で引かれる櫻井先生が羨ましいです。段位は関係なく、教えていただける方は皆、“先生”です。またいろいろと教えてください。ありがたく存じます。
この答えは魚住先生か宇佐美先生しかお答えできないと思いますが、順番に考えるのは非常に有意義な解釈と思います。
伝書には五箇の手の内を並列的に解説していて、どれが良いとは書いていません。「時の手の内」ということは場合によって、あるいは人によって使い分けよということですが、実際には難しい。
私は長い間三毒を信奉した結果、しがむ手の内が習慣となり失敗しました。強く握るのは押手を絞め殺すので、よくありません。
むしろ、これらは味わいであり、調味料のようなものであるので、貴方のような解釈でイメージできれば、最高ですね。
余談ですが、四巻の書には五箇の手の内といいながら、初勘の巻には鵜の首と鸞中の二つしか解説されていません。あとの三つは第四巻の父母の巻に解説しています。
私の勝手な想像ですが、竹林坊が書いた原本(一遍の射)を2代目の竹林貞次が四巻構成にして四巻の書としたとき、初心者にはこの二つを教え、練達者に残りの三つを教えたのではないかと思われます。
この五ケの解釈をずっと読んでいて、ふと思ったのですが、この五ケのどの手の内がよい、と言っているわけではなく、実はこの五か所は、手の内を定め、引分け、会→離れ・残身にかけての一連の流れの中の5か所の留意点なのではないか、と感じています。
1.鵜の首 は、整えるときの拇指と、小指→薬指→中指の純に整え、上開下閉にせよ
2.鸞中 は、1.のように整えても、グッと握りこむのではない、卵中の心持にせよ
3.三毒 は、引分けにかけて弓力がかかってくると、それに合わせて、それぞれが適度に締まり、拇指根の剛弱所は負けぬようにしっかり押しかけよ
4.骨法陸 は、会で上押しやべた押しや入りすぎや控えすぎにならぬ、“中四角”を意識し、弓手の手の内と弓を陸(直角)の中押しに徹せよ
5.呼立たり は、残身では弓力がかからなくなるので、その時に、握りこむような残身の手の内ではなく、力がかかれば適度に締めて、離れて力がかからなくなればまた、ふんわりとさりげない握りの手の内に戻れ
そのような流れを教示しているのではないか、と、読めば読むほど思うようになりました。
このあたりの解釈は、尾州竹林流ではどのように成されているでしょうか。