11-3 竹林流の射法
竹林流の射法は、日置流各派、吉田流の斜面と異なり、むしろ正面打ち起しと似通った射法です。
竹林流の取り懸け、手の内は正面打ち起しと同様に正面で丸く円相に構えます。弓構えは羽引きをしたまま、ほぼ平行に左へ送り、ここで引きません。押し手は肱をやや曲げて左脇腹に、勝手は体の中央で肘に張りをもたせます。この時は左に送った分だけ弓構えはひし形になりますが、これを弓懐と云い円相に構えるのが、日置流各派と大きく異なり正面打ち起しに近いのです。
これを「剛の弓懐(きゅうかい)、繋(かけ)の弦道(つるみち)」といいます。
打ち起しは斜面に引き分けながら、勝手は肘を張ったまま、弓構えから真っ直ぐ上に(左乳の上を通って)反り橋に上げ、大三を取ります。この大三およびそれ以降は正面と全く同じ位置です。
すなわち弓構えから大三に打ち起こす間を正面では縦に上げてから横に大三に至るのに対して、竹林では横に移行してから縦に上げる順序が異なるのです。
この打ち起しの違いの特徴は、竹林流は押し手、勝手の手の内が決まり易く、弓手の勢いを持たせるのに都合が良い反面、肩の十文字が崩れやすいのが欠点であるように思われます。本多翁が近代化のために変更したのはこの辺であろうと思われます。
また、押手の肘は棒のように伸ばしきるのを「突く」と言って嫌います。当流の押手の肘は「猿臂の射(えんびのしゃ)」と言って猿腕のように、円相に構えた肘のまま、肘に弾力を持たせたまま引き分けるのを大事とします。これは会から離れにおいて押手に伸び合いの余地を持たせるためと思われます。
櫻井 孝 | 2001/09/03 月 00:00 | comments (2)
| -

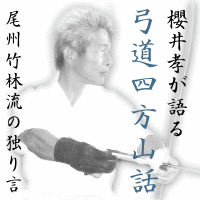



コメント
私は若いころ尾州竹林流の弓道を魚住文衛範士、魚住一郎範士に指導を受けた者であり、この「射法ドットコム」の中に「弓道四方山話」を書き始めて既に28年が経過し、この中で正面射法と日置流の斜面射法および竹林派の斜面射法について考えるうちに個人的な考えを掲載していました。この文章に対して長年が経過したが批判的なご意見は頂いていませんが、貴方のコメントにより私の文章は僭越であったことに気が付きました。
竹林射法についてお答えできるのは流派を代表する範士の先生であり、正面射法と斜面射法と竹林射法も合わせてお答えできるのは、日本弓道の全てを指導する範士の先生だけです。
従って私はこのコメントに正式に回答できませんが、「11−3 竹林流の射法」を投稿して28年が経過しているので、敢えて私の個人的な意見を書きます。
1) 貴方の解釈は私の個人的意見と概ね同じと云えます。以下は補足説明です。
2) 正面打ち起こしは「縦横十文字」の体幹を真直ぐに保つことを重視した射法である。
しかし、手の内は弓構えで整え、大三に受け渡すとき手の内を直角に廻し入れて、正しく定める必要があり、握り方によっては整えた手の内が崩れ易く難しいと云える。
3) 日置流の斜面打ち起こしでは、弓懐で弓が斜めの状態で手の内を整え、その後弓と手の内の角度変化が少ないので、手の内が定まり易い。しかし、斜面に構えて弓手を左に送るとき、体幹や両肩の線を真直ぐに保つことが判り難いと思われる。
4) 尾州竹林の斜面打ち起こしは、正面射法と日置流の斜面との中間的な射法であるので、縦横十文字も手の内の定め方も中間的であると云える。
竹林射法は弓懐で引き広げず羽引きのまま左斜面に送り、矢はなるべく平行とするのが掟であり、このとき矢と弓の角度差を考えて手の内を定める事を意識しています。
手の内は弓構えで三指を揃えて軽くふんわりと中押しに整え、弓懐では斜めに少し入れ、大三では弓の中央に虎口の中央を据えて定め、引き分けは弓のバネを受けて会に至ると考えます。
5) 何れの射法においても、まず体幹を真直ぐに保つこと(縦横十文字)が前提である。
次に左右の手の内などの働きを正しく真直ぐに柔らかく保ち、心気の働きにより自然に離れがでることが肝心であり、基本的考えは変わらないと思います。
竹林派の手の内が、他の日置流と異なる点についてですが、例えば印西の紅葉の重のように、弓構えの時点で手の内が決まってしまうのに対し、竹林派では弓構えにおける手の内が正面打起しに近く、打起しの過程で押し開きながら手の内を作り上げていく、という理解でよろしいでしょうか。