2-2 続・弓の薀蓄
洋弓の特徴は上下が対称であること、矢を左側にのせ、弓を中央までえぐっています。ゴルフのパターのように力の中心に矢が通るように工夫されていることが判ります。しかしこうすると握りの部分で弓の幅が半分になり、弓が折れてしまうのでこれを防ぐため、弓の厚さを分厚くしています。
和弓では矢は右側に番えますが、洋弓のように道具を合理的な目的のために、切り刻んで加工することはしません。
このため素直に弓を引くと弦が弓の中央に戻ろうとするので、矢はスライスしてしまいます。これを防ぐため弓は製作時に楔などを用いて横にも湾曲させ弦が弓の右側に来るように作っています。この製作時の形を入木というのは良くご存知のことでしょう。しかしこのように弓を入木にして作っても、和弓独特の射法が必要となり、初心者のうちはスライスしてしまいます。
今度は、矢のことを少しお話ししましょう。もし狩りに行ってウサギがたくさん出て来たら矢を2本番えたくなるでしょう。2本番えて引きますと、矢は半分までしか飛びません。倍の重さの矢を使うときも同じです。エネルギーから考えると当然ですよね。
矢は放物線を描いて飛んでゆきます。強い弓だと放物線のライズが小さいのでほぼ直線的に見えますが、弱い弓ではやまなりになります。また距離が遠くなると角度を上げる必要があり、遠的をすると良くわかりますね。
矢を番えないで素引きで離すと弦が切れます、また不本意ながら矢こぼれしたときも弦が切れ、顔や手を打ち、痛い思いをします。これらは矢にエネルギーが伝わらないので、弦にエネルギーがかかり切れてしまうためです。
もう一つ経験談をお話ししましょう。これもやってはいけませんが、羽のない巻き藁矢で的前を射るとどうなるでしょうか。この場合、矢は半分位までは真っ直ぐ飛びますが、途中で大きく上下左右に曲がり、行き先が定まりません。外に飛び出てしまう恐れがあるほどです。したがって巻き藁はむやみに離れて行ってはいけません。
では羽のある矢を真上に向けて飛ばすと、矢は頂点まで羽が下にあり、頂点でクルリと向きが変わり下向きになっておちてきますが、羽のない棒矢では頂点で向きが変わることなくあらぬ方向へ飛んでいってしまいます。これは羽の空気抵抗が飛行機の尾翼のように重要な役割を果たしていることがわかります。
しかし羽は鷹、鷲などの高級な羽でなくても、カラスや七面烏でも変わりなく、少々切れてボロボロになっていてもまったく変わりはありません、国際天然記念物級の鳥の羽は、連盟で将来禁止すべきと思います。
櫻井 孝 | 2001/09/03 月 00:00 | comments (0)
| -

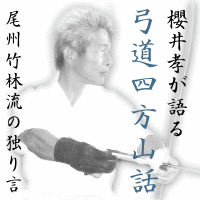



コメント