1-14 続・位なりの位とは
竹林流の「四巻の書」は名前のとおり、「初勘(しょかん)の巻、歌智射(かちしゃ)の巻、中央の巻、父母の巻」の四巻構成であり、昔は道統(流派の宗家)が修行の段階ごとに免許を与えていたものですが、その上に後継者となるべき者のみに与えられる秘伝の第五巻「潅頂(かんちょう)の巻」があり、この五巻を合わせて五巻の書あるいは本書(ほんじょ)と呼んでいます。
この本書の最後に、「受 智 修学 自師 賢覚」の八文字を八字五位と言い、「五位とは修学の位を云い、初学より至極にいたるまでの位、芸の次第を言うなり、八字の心にて知るべし」とあります。さらに「註に曰く、受(うく)は師より教えを受けること。智は己の智をもって考え、師にその善悪を質問すること。修学は実地に稽古すること。次に自師におよんでは自ら発明して機軸を出し、賢覚と悟りに入ることなり。」とあります。
そしてこの五段階は五巻の書の各段階の免許を言うのだと想像でき、この賢覚の段階まで極めたものは免許皆伝の継承者であるので、自ら発明、新機軸を出すことが許され、全てを委任すると云う意味のことが書いてあります。
こんな凄いものを写して紹介するのは、あまりにも僭越であり無謀ですが、この「本書」という秘伝中の秘伝を現代でも読めるようにまとめて紹介された先達は、多分本多流の祖である本多利実先生ではなかろうかということが本多流のHPなどから想像されます。
本多先生は旧来の弓術の秘密主義を排して、竹林流の秘伝書のみではなく、多くの流派の考えを統一して、弓道の近代化を指導された偉人です。
この本書の最後に、「受 智 修学 自師 賢覚」の八文字を八字五位と言い、「五位とは修学の位を云い、初学より至極にいたるまでの位、芸の次第を言うなり、八字の心にて知るべし」とあります。さらに「註に曰く、受(うく)は師より教えを受けること。智は己の智をもって考え、師にその善悪を質問すること。修学は実地に稽古すること。次に自師におよんでは自ら発明して機軸を出し、賢覚と悟りに入ることなり。」とあります。
そしてこの五段階は五巻の書の各段階の免許を言うのだと想像でき、この賢覚の段階まで極めたものは免許皆伝の継承者であるので、自ら発明、新機軸を出すことが許され、全てを委任すると云う意味のことが書いてあります。
こんな凄いものを写して紹介するのは、あまりにも僭越であり無謀ですが、この「本書」という秘伝中の秘伝を現代でも読めるようにまとめて紹介された先達は、多分本多流の祖である本多利実先生ではなかろうかということが本多流のHPなどから想像されます。
本多先生は旧来の弓術の秘密主義を排して、竹林流の秘伝書のみではなく、多くの流派の考えを統一して、弓道の近代化を指導された偉人です。
櫻井 孝 | 2003/02/17 月 00:00 | comments (0)
| -

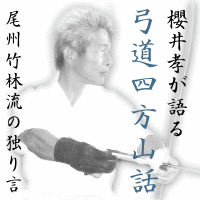



コメント