1-25 骨法、あるいは骨相筋道について(其の一)〜正射とは、骨法の射とは〜
それは確かにそうですが、正射は弓道教本の基本理念に従い、体配を習得し、射法・射技の研鑽、心気の働き、正確な狙い、自然な離れ、それら全てが整って初めて正射に至るものですので、初心のものが一朝一夕にはできることではありません。すなわち、相当な射手が心を正しく、身を正して、気を養い、正技を練り、至誠を尽くして修行に邁進して初めて、正射の高みに至る程のものです。(射法訓の前文からの引用)
したがって、練習しているのになかなか正射ができないと、卑下して諦めるのはまだ早すぎます。今の段階で正射の高みに至るのは難しいとしても、例えば高い山に登るときのように、道案内人(指導者)がいて、登山道(指導:アドバイス)を見つけ、近くの頂に目標を定め、次のステップに進むのであれば、これも正しい道と云えます。
2.骨法、および射法訓について
体を真っ直ぐに保ったまま、両肩関節をしっかり嵌め込み、矢筋方向に伸び合い、勢いのある離れが出れば、矢は狙い通りに飛ぶはずです。これを骨法と云い、的中も向上します。
「コツを掴む」という言葉がありますが、「難しい事柄でもやり方の要領を掴めば、容易にできる」と云うことであり、弓道の骨法から来た言葉のように思います。
吉見順正(紀州竹林流)の射法訓の冒頭に、「射法は弓を射ずして、骨を射ること最も肝要なり」とあり、「射法は、弓に負けないように力で射るものではなく、自分の骨格に嵌めて射ることが最も肝心である」と解釈でき、これも骨法を意味しています。
3.骨相筋道とは
竹林流の古書(四巻の書)に「骨相筋道のこと、心は七道(射法八節)の五部の詰め、始中終(射法の各段階)の骨法射形に延びて緩まざるを骨相筋道と云う義(意味)なり。矢束もこれにて知ることこれあり」とあります。
会に至り、自然な離れが出るためには「詰め合い」と「伸び合い」の二つが揃うことが絶対条件です。ここで「五部の詰め」によって十分な詰め合いを行っても、伸びが止まり緩みを生じると、緩み離れとなって会と離れが不連続になり、狂うものです。
会と離れの関係は仏教語の「会者定離(えしゃじょうり)」からの諺であり、「生ある者は定めて滅す」を意味します。
すなわち、会が良くも悪くも離れは必ず生じるが、左右が揃うときは活き離れとなり矢勢格別でも、揃わぬ時は死に離れとなり矢は飛ばない。射形が左右の肩関節に嵌って伸び合うときは、作用・反作用の法則により必ず釣り合い、働きの延長線方向に鋭く離れるが、伸び合いが緩むとき、力は不連続となり乱れる。
このことから、「骨法は伸び合いを基本とする」ものです。
4.射法八節図解
射法八節図解において、次の二か所の記述に骨法との関連を見つけました。
1)「打ち起こしにおける両腕の角度は約45度である」
次に両上腕は張りを保ったままあまり動かさず、主に両前腕を送って大三に構えるので、上腕の角度も約45度が標準となります。ここで大三が額近くに寄り過ぎると縦引きになり、馬手肱尻が前収まりになりやすく、逆に、遠すぎるときは横引きになり、両肩の線は背面側に反りやすいのです。上腕が約45度の角度であれば、馬手肱尻は回って肩関節に嵌り易いのです。
2)「会における両肩を結ぶ赤い線は矢筋の線と平行である」
ここに「両肩の線を矢に近づける」と註釈がります。こうするとき両肩関節が嵌って骨法に合致します。
櫻井 孝 | 2018/02/06 火 19:13 | comments (0)
| -

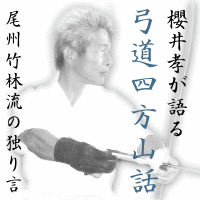



コメント