1-26 骨法、あるいは骨相筋道について(其の二)〜十文字射法について〜
1.縦横十文字
最も基本となる縦横十文字は脊柱の縦筋と両肩を結ぶ横筋とが垂直・水平方向に直交することであり、これを確実にすれば、縦軸を支柱とする天秤に、横軸を水平に働かせば、左右の力は釣り合い、骨法に叶うものとなります。
2.三重十文字
中学集という古い弓道書の胴造りに「妻肩と上肩を地縄(地紙)に重ねよ」とあります。妻肩(めかた)は腰の両骨を、上肩(うわかた)は両肩を云い、地縄(じなわ)とは足踏みの曲尺(かね:基準)であり、この上中下を筋違わぬようにすることを三つの重ねと云います。
足踏みの上に、両腰、両肩との三本の十文字を重ねよという単純な基準であり、頭で解っても、実際に弓の力が働くと、押され、押し返すとき、体は前後左右に傾き、捻じれて、この三重十文字を正直に(正しく真っ直ぐ)保つことは難しいです。
3.五重十文字
上記と同様に射法八節を遂行するには、以下の五か所を概ね直交にして力を水平に作用させることが肝心であり、これは射法の順序に従って覚えると解りやすいです。
1)弓と矢の直角(矢番え十文字)
矢番えにおいて弓の上下を結ぶ線(弦)に直角に矢を番えよと云うことです。離れて弦が弓把付近まで戻った時、弦音と同時に矢が飛び出すので、この瞬間に矢が水平となるようにするものです。ただこの時、矢は僅かに浮き上がるので、箆一本分程度上に番えるのが正しいのです。こうするとき弦を鉛直にすれば、矢は常に水平(水流れ)となります。
2)懸けの大指と弦の直角(懸けの十文字)
取り懸において、懸の大指を弦にほぼ直角に掛けよと云うことであり、残心に至るまで大指を水平方向に働かすものです。ユガケの弦枕は親指の中央に直角(一文字)にするのが標準ですが、現実には斜めに作られているものも少なくありません。その場合には親指は斜め下向きとなりますが、馬手を少し捻って親指を水平に向けるのが望ましいです。
3)弓と手の内の直角(手の内十文字)
手の内を整えるとき、弓と手の内を直角にせよと云うことであり、残心に至るまで、中押しの手の内を保つものです。しかし弓は上が長く下が短いため、弓把はやや斜めになるので、少し抑え気味(やや上押し)に働かせることが正しいのです。
4)胴の骨と肩の骨の直角(縦横十文字)
引き分けにおいて、上述の縦横十文字を保てと云うことです。
5)首の骨と矢の直角(頭持ち十文字)
会において、首の骨(筋)と矢を直角に保てとは、頭持ちを正しく的に向けるとき、首の両側にある胸鎖乳突筋の右側筋が垂直に立って見え、矢はほぼ水平であるので直交します。これは縦軸の鉛直を主としますが、狙いに密接に関わり、的中にも大きく影響します。
櫻井 孝 | 2018/02/06 火 19:13 | comments (0)
| -

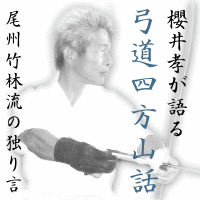



コメント