11-14 正統竹林の継承の謎
1.流派の継承
日本の伝統武芸は家系によって継承されるのが一般的ですが、竹林坊如成は四巻の書の序文において、「正直を神として法度に任せて心底に治するものには相伝すべし、たとえ親でいの弟子なりとも道に愚なる、異法に驚き、深心なきには伝ふべからず。」と記述しています。
日本の伝統武芸は家系によって継承されるのが一般的ですが、竹林坊如成は四巻の書の序文において、「正直を神として法度に任せて心底に治するものには相伝すべし、たとえ親でいの弟子なりとも道に愚なる、異法に驚き、深心なきには伝ふべからず。」と記述しています。
これは長男よりも次男の貞次が優れていたことを意識したものではないかと思われます。このためもあってか、尾州竹林流の継承は必ずしも血縁ではなく、実力のある弟子には印可を相伝したので、多くの流派に分れ発展しました。
2.唯授一人の相伝
流派の相伝には印可と唯授一人との二種類があり、印可相伝というのは免許皆伝とも呼ばれ、流派の最上位まで認可されたものですが、流派の継承には唯授一人の相伝によるものが正式なものと思われます。
3.竹林流の分派
二代目竹林貞次は家督を次男の石堂林左衛門貞直に譲り、長女の婿の岡部籐左衛門忠治に唯授一人を授けた。また通し矢で活躍した長屋六左衛門にも唯授一人を与え、紀州に仕えた瓦林與次右衛門にも印可をあたえたので、竹林流は三代目で正統竹林派、尾州竹林派、紀州竹林派の三つに分派しました。
このうち宗家とも言うべき、正統竹林派の継承については石堂竹林家か岡部籐左衛門家か諸説があって謎です。
4.正統竹林の継承と岡部派
尾州竹林流・徳風会のHPによれば、竹林貞次は子供が幼少であり弓術も未熟であったことから、家督と竹林宗家とを分けて相続させたと考えられます。
すなわち石堂竹林家の家督は岡部籐左衛門を後見人にして石堂林左衛門貞直に相続しましたが、正統竹林派の弓術師家は岡部籐左衛門が相伝したのです。その後宗家は代々の岡部籐左衛門家が明治の初めまで継承しました。これを尾州竹林流岡部派とも云います。
5.石堂家の家系断絶
その後、四代目の石堂林左衛門が殿様主催の鹿狩りにおいて、放った矢が殿様の足元に流れてしまったという不祥事が起き、石堂林左衛門は自害し、家系断絶の憂き目となってしまいました。その後、傍系の子孫が名跡を継ぎますが、竹林の栄光は途絶えてしまいました。
櫻井 孝 | 2009/04/16 木 20:01 | comments (0)
| -

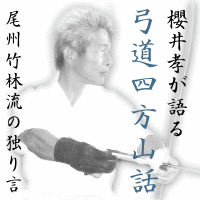



コメント