2 紀州藩通し矢ものがたり

▲射手の視点で見た堂
勘左衛門の経歴については、2004年3月号の「弓道」誌に本多流の寒川先生が「紀州藩通し矢ものがたり(4)」という論文を投稿して、勘左衛門の生い立ちが尾州と紀州の二説あり、どちらが本当なのか今後の史料研究を待たねば判らないとして、両説の概要を客観的に述べた上で、「南紀徳川史 五十九巻 武術伝 第一」からの記述を紹介しています。
妻木助九郎組の足軽星野勘左衛門は射芸をもって諸子並(足軽ではなく侍扱い)に成りたく望んだが、それほどの芸にこれなきゆえ、埒が明かず申し候につき、和歌山を立ち退き江戸へ赴き、射芸を申し立てて、尾張藩主の徳川義直卿に志願して、御射手役並に召しだされ候。これにより尾張家老の成瀬隼人は、ある時紀州藩の家老の安藤帯刀、また、後日家老の水野丹波守に会い、『星野勘左衛門というものが貴国より来り奉公を望み、当方が召抱えたので、さようにご承知給うべしと申し候』と言ったところ『その者は当方を立ち退いた不届者である。それはご勝手に御抱えなさるべく候。彼は射芸をもって諸子並みになりたくと望み候えども、彼ほどの芸は足軽の中にも大勢いる中で、そのようにはできないので、そのままに致し候。とやかく申す品はないので、如何ようにでもなさってください。』と答えた
と記述しています。これが紀州脱藩説となったものと思われます。
劇画「弓道士魂」は多分これを調べて、その意外性からストーリーを組み立てたものと思われ、史実をよく調査して書いたものと言えます。
櫻井 孝 | 2006/09/11 月 00:00 | comments (1)
| -

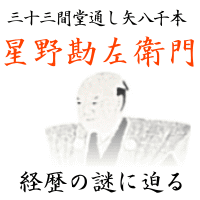



コメント
通し矢で、鬱血した相手の腕を小柄で裂いてやり
通し矢を成功させた…という
この話がベースになっている、テレビの水戸黄門の
一話があります。
東野英二郎黄門さまのころだったと思います。