12-2 好きな云葉、朝嵐の歌
「我は大日如来なりと思うべし」
「如何程も強きを好め押す力、引くに心のありと思えよ」
「ただ伸びて緩まざること」
「よく引いて曳くな抱えよ保たずと、離れを弓に知らせぬぞよき」
「鉄石相克して火いずること急なり」
「朝嵐 身にはしむなり 松風の 目には見えねど 音は涼しき」
という実に美しい歌を竹林派の伝書に見つけました。
「如何程も強きを好め押す力、引くに心のありと思えよ」
「ただ伸びて緩まざること」
「よく引いて曳くな抱えよ保たずと、離れを弓に知らせぬぞよき」
「鉄石相克して火いずること急なり」
「朝嵐 身にはしむなり 松風の 目には見えねど 音は涼しき」
という実に美しい歌を竹林派の伝書に見つけました。
私は、「清清しい朝風が松林の中を拭きぬける時、目には見えないが、さわさわと涼しげな風がしみじみと感じる。」と解釈しましたが、歌のもう一つの意味は「朝嵐のすさまじいほどの風にも松の梢は悠々としているように、射においても最上の芸は如何にすさまじく伸び合い詰めあいをしていても、森々と染み渡るように、悠々としているものだ。」と云う解釈だそうです。
ところが、浦上博子先生の「型の完成に向かって」を読んだら、日置流では「朝嵐」と云うのは、取り掛けの方法の秘伝であると全く別のことが書かれていました。
一文字の取り懸けの指使いの何が朝嵐かは良くわかりませんが、教え方が悪いと昼嵐、夕嵐になると云うような記述でした。
櫻井 孝 | 2001/09/03 月 00:00 | comments (3)
| -

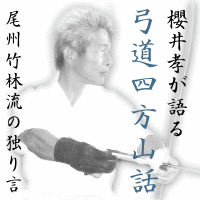



コメント
「朝嵐の歌」については、竹林流の伝書(四巻の書)の中に教歌があるので流祖竹林坊の詠んだ歌と云われていますが、日置弾正の詠んだものとも云われています。日置流の事柄は筑波大学の松尾先生や東北学院大学の黒須先生のサイトなどがあります。
竹林流では弽の弦枕の溝の位置の深浅(親指の奥が深く、指先に近いのを浅い)として、中間にあるのが「朝嵐」と呼び、溝は親指の帽子の中央に直交して、離れが軽く出やすいと云われる。深懸けは親指の根元にあり溝は斜めで、四ツ弽に用いられ「大筋違い」と呼ばれる。指先の関節付近に溝があるのを「折り目弽、小爪弽」と呼ばれ、和帽子弽に用いられる。
日置流の「朝嵐の離れ」については良く知りませんので、上記のサイトや書物で探してください。