5-19 会 -懸けの指使い-
前回の話の続きです。星野勘左衛門は「四巻之書 初勘之巻 七道 六、会」の本文を以下のように解説しています。竹林では「会」という言葉を、会と懸けの二通りにかけて云いますので、ここではもっぱら馬手の懸けの結び方を解説しています。
「一に一文字、恵休善力、一大事の口伝なり。」
一文字とは会(かけ)の大指に弦を一文字に懸けるなり。始中終つねに一文字が違えぬように懸けるべし。恵むとは大指のことである。めぐむと云うてこれより起こるところをいう。
第二指を休むという。この指しめるときは筈にさわりて矢色がつくなり。また、折りかがめてはねるのも筈にさわるなり。この休むの字は世人迷い種々のことをいっているが、休むの字の心はやすむと云うにて知るべし。形はあれどもやすむの心にて、善指(中指)になじみそえて、帽子を押さえぬほどに懸けるなり。遊ぶ指と考えるのははなはだ違っている。
第三を善指という。これは帽子を結ぶ指であり、善きほどに帽子の頭を結ぶものである。この指力むときは懸けの力みと云うて嫌う。しかしながら帽子の頭を結ぶだけでは働きがないのである。これすなわち、休む指をさし添えて善きほどに締めるなり。善指は休指の力合わせて離れるとき離れの冴え、強みともなるものなり。試して知るべし。休む指はその役目がありながら、しばらくの暇ありて守ることとしるべし。抑えるにあらず、はねるにあらず、中指に懸けて結ぶ指と知るべし。押さえ力み締めるのを嫌うなり。
力は四、五(薬指、小指)の二つの指を締めるとき、肘へ能力が至るところを知るべし。また常に肘の骨の角へものがあたるとき、すなわちその小指、薬指の二指に通じることを考えるべし。これみな骨相筋道の正法である。
「二に十文字、この十文字は総体にも口伝これあり、詰めの十文字とも云う儀なり。」
十文字というのは始め一文字に懸けた弦道が、最後まで少しも違わないように、弦と指との十文字である。
この十文字は総体にも口伝これありとは五重十文字のことであり、その条において記すものとする。この十文字懸けてより、引き納め、抱えるまで総体の五重十文字良く揃っていても、懸けの十文字にて抱えるときに、少しでも狂いがあると詰めに至ることができないので、これにより詰めの十文字が大事としるべし。この詰めの十文字が違うのは総体の十文字の規矩がすべて違って(狂って)しまうためである。
櫻井 孝 | 2005/01/22 土 00:00 | comments (0)
| -

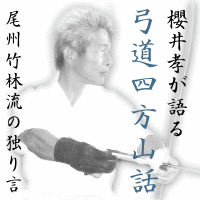



コメント