8-22 「会者定離」とは
「射法八節」における「会」、「離れ」とは、竹林流の流祖・竹林坊如成が僧籍であったため、その弓道書(四巻の書)に仏教用語の「会者定離」から名付け用いた言葉で、それが日本弓道連盟の「弓道教本」に継承されたものです。
「会者定離」とは平家物語の冒頭の名文句に「祇園精舎の鐘の音は諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色は生者必衰の理を表す」とあるように、輪廻を示した言葉であり、命あるものは必ず滅し、「会するものは必ず別れる」という仏教理念から来ています。
「会者定離」とは平家物語の冒頭の名文句に「祇園精舎の鐘の音は諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色は生者必衰の理を表す」とあるように、輪廻を示した言葉であり、命あるものは必ず滅し、「会するものは必ず別れる」という仏教理念から来ています。
足踏みから引き分けまでの全ての所業は、正しい会に納め、正しい離れに至るため、多くの法則(曲尺)を尽くし、心気の働きによって、ここに達するために行うものと云えます。
すなわち「会」では総体の十文字が、丸い円の中でいっぱいに膨らんで左右(弓手・馬手:父母)が均等に納まるとき、活きた会となり、電光石火の離れが生じ、矢(子)は活きて鋭く飛び出すものです。しかし、総体の十文字が歪むとき、あるいは緩み力むときは、片思いの会となり、鈍く死に別れの離れとなり、矢(子)は乱れます。
したがって、どんなに良くても、悪くても、必ず相応の別れは来るのですが、これには因果応酬と云って、会の良し悪しの結果が離れの生死に影響するのです。
また、竹林流では馬手の親指(定める指)を中指(善き指)の中腹で善き程に締め合わせることも、「会」という言葉を用いています。弓手の手の内と馬手の手の内が釣り合い、馬手の定指と善指の合わせが瞬時に軽く離れるとき、弓手が我知らず反応して石火の離れを生じるのです。これを「鸚鵡の離れ」と云い、至極の離れです。
馬手の「会」で締めるとき、弦は親指の弦枕に絡まってロックされているので、そのままでは離れません。離れは「指先の力を抜いて」、手のひらを返すように指パッチンと抜くと、手は開かないのに、弦は全く引っかからずにスルッと離れます。「手のひらを返す」というのは、簡単に寝返るという意味から嫌われる言葉ですが、締めている反動で弾いて手の甲を飛ばせば、瞬時に返ると思われます。
私はこんな風にやりたいと考えていますが、実際にはうまくいきません。
櫻井 孝 | 2014/01/30 木 18:28 | comments (0)
| -

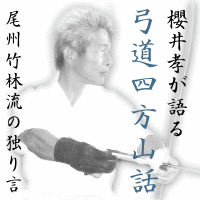



コメント