8-21 下弓が暴れる
私は普段庭の片隅の物置に巻き藁を置き、3mほど離れた花壇の通路に立って引いています。背後には芍薬、石楠花、クリスマスローズなどの高さの低い潅木があり、花の季節には良い香りがしてとても気持ちがいいです。しかし、会の状態では弓の本弭から背後の植え込みまで30〜40センチ程離れているので、植え込みには掠らない筈ですが、毎回のようにバサッと掠る音がすることに最近気が付きました。
自分では充実した会の詰め合いから軽く鋭く離れ、弓は前傾を保ったまま独楽のように小さくくるっと回るように行っているつもりでした。しかし実際にはそうではなく、下弓が暴れて大回りしているためと考えられます。ちょうど下側の芯棒の長いコマがバランスを失って、下側の軸が大きくぶれて回転するようになっていると思われます。
これは「弓道四方山話」の出発点からのテーマであり、五箇の押手も軽妙な離れも弓が小さく回ることを目指しての話でした。道路の逃げ水、二十日ねずみの回転車、バベルの塔、堂々巡りのことも書きましたが、昔に退治したつもりの亡霊がまた現れたようです。
押手を強く働かせようとして「三毒の手の内」のつもりで握りを締めたら、打ち切り射法となって弓返りが止まり、前矢が出るようになってしまったので、今度は考えを変えて「鸞中の手の内」のつもりでゆるゆると握って弓の回転にブレーキをかけないようにしました。
しかしその結果弓返りはするようになったのですが、押さえが効かなくなって、下弓が早く返って暴れてしまったのです。つまり「風が吹けば、桶屋が儲かる」のように因果関係があるように見えて、実は間違った方向に堂々廻りをしていたのです。
「鸞中の手の内」はただ緩く握るのではなく、おおとり(鷲)が卵、雛をかき抱くように、力強さのもとに柔らかく握ることと書きました。
また、今村鯉三郎先生は「弓執る心」で手の内の働かせ方を「扉の原理」として教えています。「扉の原理」とは押手の天文筋の上下を2つの蝶番とみなして弓の左の外竹に固定して、親指の角見でドアノブを推すように働かせれば、扉が開くように弓が開いて矢を真っ直ぐに押し出す考えです。
これらは、言葉として頭で理解できていても、体が反応できていないのです。離れは100分の1秒の世界、一瞬の出来事であるのでコントロールが難しいですが、会での正しい詰め合いと伸び合いができれば、安定した独楽のように小さく回るはずです。
櫻井 孝 | 2009/07/11 土 10:01 | comments (0)
| -

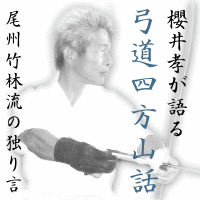



コメント