7-13 詰め合いは縮めることではない
引き分けから会に至る動きを考える時、徐々に動きが収まって来るので、詰め合いなどなくても、伸び合いだけで十分と思われます。
私は詰め合いは伸び合いの裏表の事象であり、胸の前で伸びあえば、肩甲骨は締まって来て同時に詰めあいに至ると思っています。
しかし、古書では引き分けの終点に詰め合いがあり、その後に伸び合いを持って、離れを誘うように書かれています。
したがって、詰め合いというのは引き分けの動的な動きを静かに納めて、丁度良い矢束だけ引き納め、胸弦、頬付けをピタット付け、狙いを的心に付け、両肩の関節の隙間を埋めて、気持ちを納め、きちっとホールドすることでしょう。
ここで、ホールドだけの詰め合いでは離れが出なくなりますので、伸び合いが必要になりますが、あくまでも詰め合いと伸び合いは同時に連続して行うべきと思います。
くれぐれも、詰め合いを縮めることと誤解しないようにしたいと思います。
櫻井 孝 | 2002/03/26 火 00:00 | comments (0)
| -

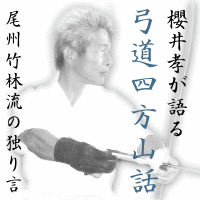



コメント