骨折後2ヶ月〜3ヶ月
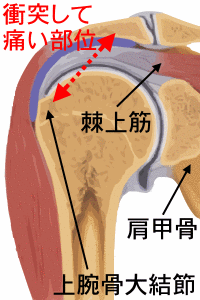
三菱病院に通院するようになって毎週レントゲンを撮りました。幸い骨折部のズレも拡大せず、医師からはここまでくれば余程大きな外力が加わらなければ骨がズレることはないだろうと言われました。骨折して2ヶ月です。少し安心しました。
また、そろそろ左肩を動かさないと筋肉が衰えるし関節も硬くなって戻らなくなってしまうとのことなので、日常生活で少しずつ左手を使い始める許可が出ました。
そこで調子に乗って弓の稽古を再開しても良いかと医師に訊いてみたところ、弓を引く動作や身体のどこに力が入るかといったことを質問されてから、無理をしなければ弓を引いても良いという許可が出ました。おお。ダメ元で訊いたのにOKが出るとは!
骨折以来、気分の晴れることがありませんでしたが、やっと腹の底から元気が湧き出てきたのを感じました。よかった、よかった。
と、喜んだのも束の間。実際に素引きをしてみると、たった15キロの弓が肩入れできません。
うーむ。これは大変なことになった。再び心に暗雲が垂れ込めました。そういえば人間の筋肉は2ヶ月使わなければ元の力を殆ど失うと聞いたことがあるような…。
失ったものは仕方ありません。気を取り直して少しずつ取り戻すしかありません。慣れてくるとなんとか肩が入るようになってきましたが、二三度素引きをしただけで鈍痛がして左腕が痺れ、押手の力が抜けていきます。やはり、まだ弓を手にするのは早かったようです。そこで当分は騎射体操だけにすることにしました。
小笠原流の騎射体操というのは騎射の稽古の基本です。馬の鞍に跨った形に腰を落として(鞍ハマリといいます)中腰のまま徒手で弓を引く動作をします。中腰といってもただの中腰ではなくて、股関節をしっかり開きいて一旦上体を水平に前傾させます。相撲の仕切の姿勢とよく似ています。この構えから胸を垂直に起こすようにします。強烈な出尻鳩胸スタイルですね。この体勢で腰の上に人が跨ってきてもビクともしない胴造りとなるように稽古するわけです。これを真剣に10回もやると相当堪えます。
さて、骨折後3ヶ月のレントゲンを撮ったところ骨自体は経過良好でした。シャツや上着を羽織る動作などではかなり痛むことがありますが、1ヶ月前と比較して肩の可動域は随分広がってきたのを感じます。筋肉の強ばりが取れてきたのでしょうか。
ただ、関節内に引っかかり感があって、肩を回す方向によってはポキポキとかボキボキという音がします。これは骨折部分に小さな骨のかけらが残ってしまったことと、関節内の炎症が治まっていないため腫れや癒着があるためだそうです。しかし、炎症が無くなるには最低半年くらいかかるのが普通なので、気にせずリハビリしなさいとのこと。
そこで弓の稽古もワンステップ進めて、騎射体操に加えて少しずつ素引きをすることにします。
そこで気になったのは弓構えをすると左右の肩の高さがまるで違うことです。自分では肩を釣り上げている感覚は全くないのに、鏡を見ると何故か左肩が高いんですね。
これを医師に尋ねたところ、肩関節(上腕骨と肩甲骨を繋ぐ関節)が動きにくいと、自然に肩甲骨の動きで補おうとするため肩が上がるのだそうです。
腕の上げ下げは肩関節と肩甲骨の回転で実現しています。もともと肩甲骨は上腕骨が動くとそれに伴って動くのですが、ローテーターカフ(腱板筋群)が弱っていると腕を横から上げること(上肢の外転)ができず、それを補うために肩甲骨が上方旋回するので肩が高くなるのです。
肩関節30度以上の動きでは、上肢の外転2度毎に肩甲骨が1度ずつ上方回旋するのだそうです。例えば、腕を真横(90度)に上げる=肩関節外転60度+肩甲骨旋回30度となります。この2:1の共同運動を「肩甲上腕リズム」と呼びます。
三角筋や僧帽筋といった外側にある筋肉はアウターマッスルと呼ばれ、それに対してローテーターカフ(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)は内側にあるのでインナーマッスルと呼ばれます。インナーマッスルは筋肉の種類で言うと「遅筋」で、大きな力は出せませんが持久力に優れています。そのためローテーターカフは肩関節の安定性を保つ役割を担っています。
これらのバランスが崩れて肩甲上腕リズムが狂うとインピンジメント症候群という障害が発生します。この障害がひどくなると腱板断裂になったり大結節剥離骨折になったりするのです。
インピンジメント(impingement)とは衝突という意味です。インナーマッスル(ローテーターカフ)の働きが不十分だと、上腕骨を外転させきらないうちに肩のアウターマッスル(主に三角筋)が腕を引き上げてしまって、大結節の部分が肩峰(肩甲骨の上端、鎖骨との接続部)に衝突して周囲の筋肉等を挟み込んで損傷するのです。
ローテーターカフのうち棘上筋は肩関節を中心として上腕骨を水平まで引き上げる働きをしますが、このとき肩関節が上へ外れないように上腕骨と肩甲骨を結ぶ棘下筋と小円筋が働いていないと安定しません。つまり支点を安定させるわけです。この安定性が失われたときに最も損傷を受けやすいのが棘上筋です。軽度のインピンジメント症候群では、この棘上筋の部分で炎症を起こすことが殆どだそうです。
昔から弓引きの人々が悩む肩痛は、多くの場合このインピンジメント症候群のようです。
このインピジメント症候群を予防するためには、アウターマッスルだけを鍛えるのではなくて、インナーマッスルもバランス良くトレーニングすることが必要です。インピンジメント症候群になってしまった場合も、インナーマッスルを鍛えることで回復が早まるそうです。故障したプロ野球の投手がリハビリでゴムチューブを引っ張っていたりしますが、あれはインナーマッスルを鍛えているのです。
アウターマッスルを鍛えるトレーニングは高負荷低回数、インナーマッスルを鍛えるには低負荷高回数がセオリーです。例えばウエイトトレーニングであれば軽いウェイトのダンベル等をゆっくり何度も持ち上げるとインナーマッスルを鍛えることができます。ゆっくり動かすところがポイントです。速く動かすとアウターマッスルが働いてしまうからです。
速筋であるアウターマッスルは大きな力や瞬発力を発揮します。つまり力を入れようと意識したときにアウターマッスルは働きますが、それに対してインナーマッスルは力を抜いて動作するときに働きます。
しかし、スポーツトレーナーの世界でもインナーマッスルの重要性に注目し始めたのは最近らしく、まだインナーマッスルを確実に鍛える方法は確立されていないようです。
峯 茂康 | 2006/12/31 日 11:20 | comments (0)
| -





コメント