12-8 浦上先生、稲垣先生の本
1. 型の完成に向かって
浦上博子先生の「型の完成に向かって」と云う本を見つけました。この本は雑誌「弓道」に連載したものを単行本にしたもので、知る人ぞ知る有名な本でした。冒頭の写真は日置流の真髄が伝わってくる凄いものです。
浦上博子先生の「型の完成に向かって」と云う本を見つけました。この本は雑誌「弓道」に連載したものを単行本にしたもので、知る人ぞ知る有名な本でした。冒頭の写真は日置流の真髄が伝わってくる凄いものです。
しかし書の中身は、日置流道統の伝書や云い伝えを解説するものではなく、全て自分の射の経験で得たものを、自然に優しく書いている所が凄いと思います。とくに勝手の指使いや押手の手内の解説は微妙な所が表現されています。
後半では経験と修練における精神的な重要点について、優しく指導しているのは絶品であると思います。
2. 紅葉重ね・離れの時期・弓具の手入れ
故浦上栄先生の「紅葉重ね、離れの時期、弓具の手入れ」を浦上博子先生が、改訂して再発行したものです。この本は弓道の射技の真髄を判り易く理論的に、図解的に説明しています。もちろん日置流ですので、斜面打ち起しですが、正面打ち起しの人にも参考になるはずです。
「紅葉重ね」と云うのは理想的な手の内のことであり、何故角見を効かす必要があるか、そのためにはどうするのが合理的かを追求したのが日置流の手の内であり、最も単純かつ効果的な射法であると云えます。
「離れの時期」については、引き分けて会、離れに至るとき、「詰めあい、伸び合い、やごろ」に分けて判りやすく教えています。これは離れにおける微妙な働きの極意であり、あるいは弦から矢が分離する一瞬の経過を、判りやすく高速度撮影で説明しています。また伸び合いの後にまさに離れるやごろにおいて、懸けから生じる「キチキチキチキチーキチーパン」と鳴って、押手が4寸(12センチ)勝手が8寸(24センチ)矢筋方向に開いて離れると説明しています。(原文どおりではない)
3. 絵説{弓道}
故稲垣源四郎先生の本であり、浦上先生の本の実践版と云うべきでしょうか、稲垣先生の高速度写真のコマを忠実に描いた絵を元に、弓道の真髄を説明しています。
最初は角見の働きについて、次に離れの瞬間における弦の別れについて、詰めあい伸び合い、「やごろ」について絵で詳細に解説しています。
また射礼については、礼射系とともに、日置流独特の矛突き(竹林では中墨の構え)、的割りの構え、二足の足踏みについて詳細に絵で説明しているのが貴重です。
また、この本の凄いところは、弓道におけるあらゆる悪癖の数々を絵に示しながら処方箋を書いている所です。中級の人にはうってつけの書といえます。
櫻井 孝 | 2001/09/03 月 00:00 | comments (2)
| -

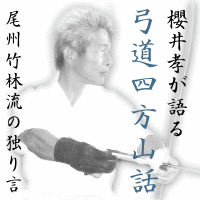



コメント